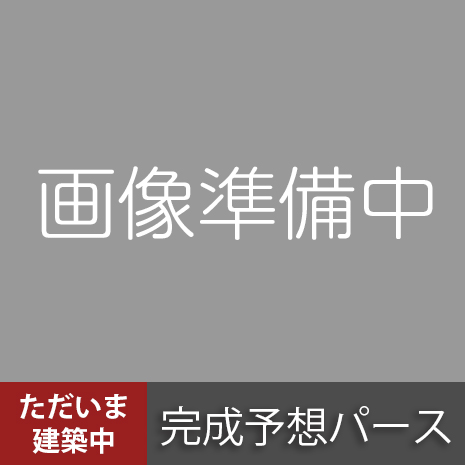お知らせInformation
-
2024.04.08
お知らせ
-
2024.04.04
お知らせ
はじめての方へStart building a house

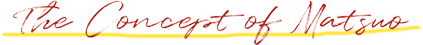
建てた後の暮らしを一番に考える
私たちのミッションは、家族が笑顔になる家づくり。
そして、建てた後もずっとオーナー様の幸せがつづくこと。
アイムホーム松尾工務店では、安心して返済できる金額で、一級建築士が希望をカタチにします。


Make House私たちの家づくり


スタッフStaff
わたしたちがお手伝いします!
アイムホーム松尾工務店は小さな工務店ですが、設計、工務、コーディネーターが連携して、お客さまの幸せな家づくりのために全力でお手伝いします。

- お金のこと
- 土地のこと
- 間取りのこと
- など
一級建築士に直接相談できる
無料相談会
 見学会・勉強会
見学会・勉強会